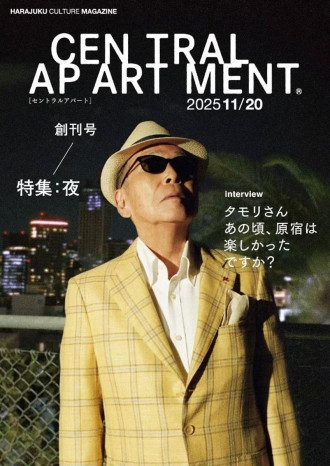個性的なワークスタイルとリンクする
渋谷SOHOオフィス事情
■SOHOの誕生と発展
「Small Office Home Office」(スモールオフィス・ホームオフィス)を略した「SOHO」という呼び名が日本に上陸したのは1995年と言われている。言葉としての語源は、ニューヨーク・マンハッタン南地区のソーホー街(South of Houston Street=SOHO)にある。1960年代後半からこのエリアに若きアーティストの卵が集まり、アートや音楽など創造的な活動を始めるようになり、1980年代から90年代にはパソコンの普及、インターネットの発展に伴い、コンテンツクリエーターをシンボルとする、パソコンを駆使して場所や空間を超えた新たなビジネスを生み出そうとする一群が登場する。そこで在米のマーケッターが地区名のSOHOに「Small Office Home Office」を当てはめ、彼らを「SOHO」と称した。これが日本にも波及する“SOHOブーム”の起源となる。
カンパニーという概念より小さいので「スモールオフィス」、仕事場と住居とが一致しているケースが多いことから「ホームオフィス」と続けてくくられたが、自己責任に貫かれた“個人主義”に根ざす米国にはもともと「ホーム・ベースド・ビジネス(自宅を拠点とする事業者)」や「インディペンデント・コントラクター(独立系契約者)」と称されるフリーランスが多く存在していたことから、「SOHO」は主にインターネットを背景に語られるマーケット用語として用いられた。今日、日本で総称される「SOHO」の文脈とはやや異なると言える。
「SOHO」という言葉が日本に上陸した際には“アメリカ式のユニークなワークスタイル”と伝えられたが、自宅を仕事場とするワークスタイルそのものに新しさはない。日本でもフリーランスのデザイナーやアーティスト、作家、開業医、建築家、会計士や税理士など「士」業の多くは明治時代から「自宅で仕事」をしていた。それにもかかわらず「SOHO」が日本で脚光をあびた背景には、不況に伴う「リストラの受け皿」という側面がクローズアップされたこと、独立起業した「ベンチャー」のアーリーステージとの混同、主婦のサイドビジネスである「在宅ワーカー」の増加などが挙げられる。
マスコミが先行する“SOHO ブーム”を受けて、1990年代末には政府がSOHOの実態調査を開始。1999年にはSOHOと政府・行政・企業との橋渡し役となり、政策提言、調査研究、会員サービス開発などの活動を行う任意団体が設立。2000年12月には、財団法人日本SOHO協会(略称J-SOHO)が全国規模の公益法人として政府に認可され、設立、代官山ヒルサイドテラスに事務所を構える。J-SOHOではSOHOを「ITを活用して事業活動を行っている従業員10名以下程度の規模の事業者のこと。主にクリエイター、フリーランス、ベンチャー、有資格者、在宅ワーカーなどが対象」と定義付けている。
J-SOHOによれば、国内に約500万事業所(法人188万、個人315万)、約1,500万人以上が就労し、SOHO事業維持経費市場は約21兆円規模と推定。J-SOHOが調査結果をまとめた「SOHO白書2002」では、SOHO事業者の平均年齢は41.2歳、脱サラ・リストラ族が中心とされている。業種業態のベスト3は以下の通り。
- 建設・環境・インテリア設計 10.6%
- システム開発・プログラム 9.5%
- Web制作・デジタル 8.3%
主に仕事を行っている場所は「専用オフィス」より「自宅(兼用)」が多く、「最小限の資金でまかなうためには止むを得ない選択」としている。
J-SOHOは会員制度をとっており、正会員には事業証明書(SOHO-ID)の発行のほか、慶弔見舞金・保険制度の適用、正会員メーリングリストへの参加、SOHO事業者データベースの利用など特典がある。入会金3,000円、年会費12,000円。
財団法人 日本SOHO協会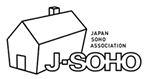
■渋谷の一等地にオフィスを構えられる、レンタルオフィスの需要
SOHO事業者やベンチャー企業向けの高付加価値スモールオフィス、通称「レンタルオフィス」も人気が高い。「レンタルオフィス」は一等地に低コストでオフィスが構えられることや入居者が1人でも対応してくれること、オフィス設備の完備やサポートサービスが受けられるなどのメリットがあり、都心にオフィスを構えたいユーザーに好評を博している。渋谷エリアには10社以上が進出しており、すでにマーケットとして確立しており、多くは敷金・礼金・保証金、仲介手数料など初期費用がかからないシステムを採っている。
渋谷、表参道、南青山でレンタルオフィスを展開する「オープンオフィス」(経営=ビジネスバンク)は、中でも急成長を遂げる1997年創業のベンチャー企業。同社社長の浜口さんは「新たに事業を始める人をサポートするのために何ができるかを考え、オフィスの需要が求められていることからサービスの提供を始めた。“職住”の分離希望者、初期投資とランニングコストの軽減を望んでいるSOHO事業者やベンチャーに応えたい」と語る。契約者は法人が6~7割を占め、規模は「スモール・カンパニー」が多い。業種業態としてはIT関連系、コンサルタントなどが5~6割を占め、大手企業のプロジェクトチームや支店が3割を占める。レンタルの期間は平均1年。短い契約者で3ヶ月。
「オープンハウス」の契約者は、クリエイターよりビジネスマンが圧倒的に多いのが特徴。浜口さんは「“ガレージ・ビジネス”が成り立つアメリカとは異なり、日本にはガレージのある家は少ない。日本の住宅事情がネックとなり、自宅で開業しにくいのが現状。“職住一体”“職住分離”は、ライフスタイルや趣味の違いでもあるが、レンタルオフィスは次のステージへ向かう過渡期の利用者に好まれる傾向がある。渋谷に事務所を構えてある程度の成果をあげたら、次にきちんとした賃貸オフィスに入居するもよし、自宅に事務所を構えるのもよし。渋谷はそういった選択肢にあふれている街とも言える」と、レンタルオフィスのポジショニングをまとめる。現在、空室となっている表参道の「オープンオフィス」(地下鉄表参道駅徒歩0分)の価格(使用料+共益費)は、月額17.8万~22.8万円。100Mbpsの光ファイバーが設備されている。
オープンオフィス

■都市公団が実施する“職住”一体のSOHOスタイル
“職住一体”のSOHO住宅も普及しつつある。都市公団も時代のニーズに応え、初めてSOHO 住宅(施設付賃貸住宅)を手がけた。都市公団が示すSOHO住宅とは「居住専用である住宅部分に隣接して、業務専用スペースとなるワークスペースを設置して、住宅部分とワークスペースを一体で入居者へ賃貸するもの」。最初の物件「シティコート目黒」(品川区上大崎)はJR目黒駅から徒歩5分という立地。都市公団総合募集センター住宅募集部によると、第1次募集(2002年4月13日~30日)は募集戸数6戸に対して499人(倍率83.2倍)もの申込者数があったという。続いて6月8日(土)~24日(月)、第2次募集を行う。
「シティコート目黒」のSOHO住宅の特徴
- オフィス専用玄関とプライベート専用玄関を分離(庭側がオフィス、廊下側がプライベート)(公私の区別ができること、オフィス訪問者のアクセスがスムースになるなど利点)
- オフィス部分には専用回線を準備(住宅部分のインターネット配線とは別に、ブロードバンド対応のインターネット回線が設置可能)
- オフィス部分は最大100アンペアまで電気容量が可能 ・中庭エントランスに設置された集会室が、うちあわせスペースとして利用可能(有料)
第1次募集で最も人気の高かったプランは、2LDK(87平方メートル)+ワークスペース(15.79平方メートル)家賃266,070円。夫婦+子供1人までなら暮らせるスペースである。入居者の条件に個人事業であること、定められたワークスペース以外での業務ができないことなどがあるが、単身者の入居や個人事務所名の掲示は可能(表札の設置可)。第1次募集では、約3割がIT関連ワーカーであるという。
都市公団
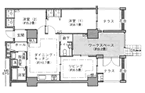
■クリエイターに人気のデザイナーズ物件
デザイナーズマンションのプランニングと仲介を営む「リネア建築企画」(南青山)には、入居を希望するクリエイターからの問い合わせが多いという。それらの物件はSOHO向けとして大々的に告知しなくても、常にアンテナを張り巡らせているSOHO事業者やスモールオフィスを営むクリエイターの目にすぐにとまるのである。企画営業部の奈良原さんは「雑誌などに取り上げられることが多いのでデザナーズマンションの数も多いように思われがちだが、実は扱う物件の全体の1%に満たない」と話す。「普通のマンションは、戸数は多いが契約に至らない。戸数の少ないデザイナーズマンションは、空室が出るのを待っている入居希望者も少なくない」のが現状である。
デザイナーズマンションが注目されるようになった背景には、バブル崩壊後、グレードの高いマンションが以前より安い賃料で市場に出回るようになり、インテリアや居住スペースを意識し始めた若い層に浸透していったことがある。「かつてのオーナーとは異なり、今日では地主の息子、娘がデザイナーズマンションの存在や著名な建築家の名前を知っているので、以前に比べてデザイナーズマンション建設のプレゼンテーションがしやすくなったのは事実。近年、オーナーの意識は確実に変化している」と、奈良原さんは傾向を語る。「デコラティブなマンションより、何も手を加えていないスケルトンに近いマンションに人気が集まっている。入居者が個性を出しやすい空間、インテリアを工夫しやすい空間が求められている」とまとめる。
リネア建築企画「シドニー現代美術館新館」や「アルメア文化センター」(オランダ)などを手がけるなど、国際的な評価も高い建築家の妹島和世氏が設計を手掛けた、恵比寿1丁目にある鉄筋コンクリート造7階建て賃貸マンション「Saito(サイトー)」は、事務所としても使用できることから、カメラマン、デザイン事務所、IT関連会社などクリエイティブに携わる会社や個人事務所が入居している。オーナー家族と1室以外は、すべてクリエイターが事務所として使用しているクリエイターズ・マンションである。外壁はコンクリート打放し。1階はオーナーでもあるガラス会社の事務所となっており、パンチングメタルのシャッターが目隠しの役目も果たしている。妹島氏は住宅の設計を手掛けないため「Saito」は稀有な物件でもある。妹島氏が得意とするガラスを駆使したデザインはここでも存分に発揮されている。
同物件を扱う大木不動産(恵比寿)の担当者である阿部さんは「妹島さんが手がけたデザイナーズマンションということもあり、人気は高い。入居希望者のほとんどが外観を見ただけで気に入る様子。中には『他の物件ではダメ。これしかない』という熱狂的な希望者もいる」と話す。「Saito」の内装は無駄を廃除したミニマムなデザインで、バス・トイレがスケルトンとなっているのが特徴。入居者はカーテンを使用するなどして工夫をしているという。5月24日現在、401号室のみ入居可。49.7平方メートル、賃料27万円。管理費なし。問い合わせは多いという。
大木不動産一般の人にとってかつては接点のなかった建築家やデザイナーが広く認知されるようになった背景には、ここ数年、都心部に住む20代~40代がインテリアや住居に大きな関心を示すようになったことが挙げられる。日本の住宅事情はこれまで劣悪な状況であった。ファッションや音楽に長けた現代人、特にクリエイティブに携わる人間が仕事のスペースに大きな関心を寄せるのは当然のことである。ライフスタイルから切り込む住宅専門誌、建築専門誌も増え、有名な建築家の物件が紹介される一方、人気のアパレルショップやレストランを手がけたデザイナーが脚光をあびるなど、“裏方”が表舞台に登場した今日では、「安藤忠雄氏に自宅を建てて欲しい」、「あのレストランをデザインした人に自宅をプロデュースして欲しい」といった指名も増えているという。建築やインテリアの情報を吸収した個人と、現代人にとって快適な空間を構築したいと考える建築家やデザイナー、マーケットの要求に応える物件をプランンニングする企業がワークスペースや居住空間を変えつつある。


■SOHOが選ぶオフィス・ファニチャーとは
もともと自立心が旺盛で、自己主張の激しいSOHOワーカーは、一般企業のようにお仕着せのオフィス家具では満足しない。一般企業のオフィスのレイアウトは、少数の管理職が複数の部下を管理しやすいようなピラミッド型の配置となっており、当然のことながら家具や什器を社員個人が選ぶことはできない。それでは、自立するSOHOワーカーはどのようなオフィス・ファニチャーを求めているのであろうか。
青山通りにオフィス家具の専門店「Work styling」を構え、オフィスプランニングも行う「アルバ」(渋谷)社長の佐藤さんは「SOHOワーカーの要望は、既存のオフィス家具の否定から始まっている」と切り出す。かつてグレー一辺倒だったオフィス家具にカラー化の波が押し寄せたのが、1970年半ば。しかし、色がベージュに変わっただけで、どこのメーカーが作っても色が同じという時期が続いた。「そこから脱却したい。家具の色が自由に選べる、収納の選択肢があるなど、選んだ家具でも自分らしさを表現したいというSOHO向けの家具がやっと今日、日本でも製造されるようになった」という。
「現実的には、スモールオフィスの場合、資金は少ない。ちゃんとしたオフィスを借りたいが、マンション形式のオフィスで我慢している。嫌なことは廃除するが、家具を全部揃えることはできないので、一品豪華主義になる。たとえば椅子だけはイームズやハーマンミラーを買っていくというスタイルが見受けられる」と、佐藤さんはスモールオフィスの現状に照らし合わせて需要を分析する。同店では、狭いスペースに家具を搬入することが多いので、コンパクトな大きさの家具や複数の機能を持った家具を揃えるようにしている。求められるオフィス・ファニチャーの条件は、色や大きさに選択肢があることが挙げられる。
顧客は青山通りという立地もあって「自由な感じの人が多い。ネクタイした人は来ない」(佐藤さん)。同店のデータでは、個人ユーザーが30%、SOHO事業者や10人くらいのスモールオフィスの需要が50%を超えているという。「渋谷はIT関連企業で、スモールオフィスが多いのが特徴。彼らに最適な家具を提案していきたい」と、佐藤さんは抱負を語る。
アルバ

キャットストリートの中ほどにインテリア・ギャラリーのようなショップ「hhstyle.com」(神宮前)がオープンしたのは2000年9月。世界中の著名なデザイナーの家具を購入することのできるショップとして瞬く間に広く認知された。設計は建築家の妹島和世氏(前出)。同ショップは妹島氏が東京で手がけた初のパブリックな建築物で、全面にガラスを配したデザイン、スロープの穏やかな階段など、建物自体が同ショップのコンセプトを明言していることも話題にのぼった。プレスの石野田(いしのだ)さんは「もともとSOHOに対応できるショップを目指した」と話す。「確かにデザイナーや建築家など、クリエイターの需要が多い。クリエイターはインテリアへのこだわりが強く、かついいものを見る目を持っている。彼らがアーロンチェアやイプシロンなどの椅子を選び、それを見た若い世代は、そこでブランドを意識するようになったようだ」と分析する。
同店では、デザイナーの椅子のほかに、好みに応じてレイアウトができる、イームズの組み立て式の棚が人気を集めている。シンプルだが、カラーバリエーションに富んでいるのが特徴である。同店の顧客は圧倒的に男性客が多い。「男性のほうがインテリアへのこだわりを持っている。洋服と同じようにインテリアに興味を持つ人が最近富みに増え、部屋の雰囲気を変えるために、気に入ったデザインのアイテムを取り入れてコーディネートする人が増えている」という。石野田さんは「会社もオフィス・ファニチャーで個性を表現することが可能。意志決定のしやすいスモールオフィスなら商品を選ぶのも素早い」と、スモールオフィスのメリットにもふれる。
hhstyle.com

海外はもとより、日本でもSOHOワーカーやスモールオフィスで圧倒的な人気を博しているのが「ハーマンミラー」の“アーロンチェア”。“アーロンチェア”はすべての体格・体形にぴったり合うように配慮された椅子で、機能を形にした刺激的なフォルムや大胆なリクライニングが可能なこと、メッシュがフット感を生み出すことなど多くの魅力を兼ね備えた名品。パソコンを駆使するデザイナーやプログラマー、SEらが利用し、“長時間座っていても疲れない”と証言したことで、クリエイターの間では数年前から認知されていた。
「ハーマンミラージャパン」(五反田)マーケティング部の前澤さんは「アーロンチェアが日本で発表されたのは1994年。長い期間を費やして生まれたアーロンチェアは、どんな人でも快適に座る権利がある、というコンセプトで開発された。発表以降、メディアでも取り上げられる機会が増え、クールなデザインが若者を中心に人気となり、個人ユーザーから大企業に至るまで認められるようになった」と説明する。同社ではオフィスを「生活の一部である有意義な場」と位置付けている。「快適なオフィス環境を用意することがスタッフのポテンシャルを上げ、結果として事業の成果も上がる」という考え方は、日本の企業に欠けていたコンセプトである。
前澤さんは最近の傾向として「日本でも自分の個性や会社の個性を表現するアイテムとして家具が受け止められるようになってきた」ことを挙げる。クリエイティビティーを刺激するファニチャーがオフィスに必要であることを、やっと経営者が気づきつつあるようだ。「家具の中で椅子は、オフィスワーカーにとって重要である。会社の規模にかかわらず、働く環境が重要と考える人は、機能的で優れたデザインの椅子を選んでいる。また、会社が大きく変化する際に家具を変えることでスタッフの意識も変革しようと意欲する企業もある。そこで働くスタッフも自分が大切にされていると感じるし、きれいなオフィスを見れば入社を希望する人も増える」と、特に椅子の重要性と、椅子がもたらす有形無形の効果を語る。
ハーマンミラージャパン

「X-girl」や「ワイアード・カフェ」など人気店を手がけ、そのパネル工法でも話題となった建築プロデュース会社「LDK」(神宮前)は近年、新たなシステムによる住宅の設計など、建築・インテリアのプランニングを主に行っている。代表取締役副社長で建築プロデューサーの玉田さんは、SOHOの文脈とは異なるアプローチで新たなオフィス空間、居住空間を提言する。「需要を勝手に想像してハコを先に作っていって、後で人を埋めていくという発想でなく、活性化している自由な人たちの発想に必然的に付随するハコが、本来理想的なオフィスのありかたのひとつだと考えている」と前置きし、「コーポラティブハウス」の可能性をひもとく。“コーポラティブハウス”とは、複数で土地を購入し、建築家と直に交渉しながら自分たちの好みに応じて内装や外装、居住スペースやワークスペースを作り上げていく集合住宅。「自由な人たちがソフトを前提としてコラボレーションをする。それは高度に分業化し、専門化したところをもう一度総合的な提案を実施していこうということの表れ。共同体やムラ、近所つきあいの概念とは異なり、建物の中のルールを前提とした新しい賃貸のあり方があるはず。これが発展すると、クリエイティビティに満ちた都市空間、界隈という建物のあり方となる」(玉田さん)。
「SOHOと呼ぶのが相応しいかどうかわからないが、新しいオフィスのイメージとして、象徴的な言葉として思い浮かぶのがコーポラティブハウス。異業種が集まり、お茶を飲むスペースやノウハウ、機材を共有するスペースもプランの中では前提とする。費用を出し合うが、スペースを何分割かする“シェアする”の発想でなく、プラスアルファを創造していくスタイルに注目している」と玉田さん。それを実現するために、同社では簡易でスピーディにできる建築工法を提案している。「LGSパネルシステム」と命名された工法で、柱と梁の構造をパネル単位にし、“レゴ”を組み立てるようにして建物を組み立てていくもの。この工法を用いると、オフィスや住居は自在に“増殖”する。「お仕着せのSOHOでなく、クリエイター自身が自然発生的に増えていくのが渋谷。求められているのは、ナニナニ風でないごく当たり前の空間、不要なデザインをしない空間。これで土地が供給されればおもしろくなる」と、玉田さんは近未来的なオフィス空間の可能性を示唆する。
LDKビジネススタイルはライフスタイルとともに変貌しつつある。「雇われない生き方」「自立した生き方」「個性を全面に出せる生き方」を選んだ少人数の人間が“SOHOスタイル”を実践する時、彼らはまずお仕着せのオフィス空間や家具を否定する。「ホームオフィス」と呼ばれる自宅で仕事をする“ワークスタイル”も「スモールオフィス」と呼ばれる小さなオフィスで営む“ワークスタイル”も、余裕と創造性をもたらすものでなければならない。カフェ人気を反映して、ファッションと同じようにインテリアに高い関心を持つ20~30代ワーカーが、今度は仕事場に“こだわり”を持ち始めている。
彼らにとってオフィス空間は“ただ働ければいい場所”というだけではなく、ワークスタイルを含めた一種の“プレゼンテーション”の場でもある。最近では、スタッフがDVDの鑑賞もできる、プレゼン用の映像設備をオフィスに設ける経営者、オフィスにカフェのコーナーやDJブースを設置する若い経営者も登場している。一見、趣味の延長線上に見えるSOHOオフィス空間も、「創造力を生み出す場」「プレゼンの場」「差別化を図るための場」あるいは「感度のいい人材を確保するための場」といった、クールに計算された独自のバランス感覚の上に成り立っているとも言えそうだ。