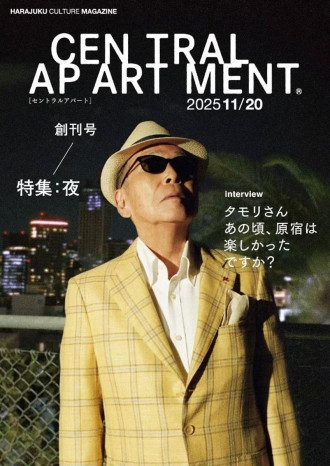消費者視点で浸透する食の新スタイル
渋谷「オーガニック・スタイル」事情
■農水省が定める「オーガニック」のガイドライン
英語の「ORGANIC」には化学用語で「有機の、炭素を含む」の意と、一般用語の「有機的な、生物体の」の意、さらに「基本的な、本質的な」という意がある。最近よく見かける「オーガニックフード」や「オーガニック料理」は、有機農法・有機栽培による農産物やそれを使った料理を示す。農林水産省では、こうした「オーガニック」と呼ばれる「有機農産物」と、これに似た存在として認識されている「特別栽培農産物」にかかわる表示ガイドラインを次のように厳密に定義している。
それによると「有機農産物」とは、「化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本としてばん種または植付け前2年以上の間、堆肥等による土作りを行ったほ場において生産された農作物」のこと。わかりやすく説明すると、化学合成農薬や化学肥料を使わなくなってから3年以上経った田畑で栽培され、収穫されてから流通される間にも合成化学物質に汚染されないこと、他の環境で栽培された農作物と混じらないようにすることなどが必須条件となっている。こうした「有機農産物」は日本農林規格(有機JAS)により、以下のような名称で表示されるよう規定されている。有機農産物、有機栽培農産物、有機農産物○○、○○有機農産物、有機栽培農産物○○、○○有機栽培農産物、有機栽培○○、○○有機栽培、有機○○または○○有機、オーガニック○○または○○オーガニック(○○には一般的な農作物の名称を記載)。
一方「特別栽培農産物」には3つの表示が定められ、それぞれ次のように定義されている。(1)「無農薬栽培農産物」(=栽培期間中、農薬を使用しない栽培方法により生産された農産物)、(2)無化学肥料栽培農作物(=栽培期間中、化学肥料を使用しない栽培方法により生産された農産物)、(3)減農薬栽培農産物(=栽培期間中、化学合成農薬の使用回数を、当該地域の同作期において慣行的に使用されている回数のおおむね5割以下にして生産された農産物)。ガイドラインにある「無農薬」は、栽培中に農薬や化学肥料を使わない農産物のことだが、栽培する以前や収穫して流通する間の環境については言及していない。つまり「無農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などは栽培期間中にのみ着目した表示方法であって、「有機農作物」と「特別栽培農産物」の定義には違いがあることがわかる。
農林水産省■渋谷周辺エリアの「オーガニック」先駆者たち
オーガニックの販売面では、渋谷や青山界隈は全国的に見ても先駆者的エリアと言えそうだ。「オーガニック」や「有機農産物」という言葉が定着、浸透し始めたのは雑誌やテレビで使われ始めた1990年代後半だとされている。それ以前から自然食品や自然化粧品の販売を行ってきたのが、北青山の「ナチュラルハウス」(本社:港区)。1982年に設立された同社は、同年3月に「ナチュラルハウス青山店」を開店。当時は「オーガニック」という言葉でなく、「自然食品」という表記であった。その後、エコロジーへの関心の高さとともに業績がアップし、現在では全国に13店舗を展開している。取り扱いアイテムは、自然食品、自然化粧品、生鮮食品、ダイエット食品、メディカルハーブ、減塩食品、機能性食品など。
ナチュラルハウス1980年代にすでに「オーガニック」の見地から最適な食事を提供するレストランの開業を考えていた整体指導者の南清貴さんが、自身の名前を冠した飲食店「キヨズ・キッチン」を元代々木町に開店したのは1995年。整体指導者の南さんは1980年代の半ば、体調不良を訴える方のカウンセリングをしている際に「ひとり一人の症状は異なるが、おしなべて共通点のある症状を見せていた。整体的に同じくくりにできた」と回想する。その共通点とは食べ物のこと。2週間、各自が口にしたすべての食べ物のリストを分析し、体調不良の要因が油と砂糖にあることを見いだした。「油は脂肪分解酵素であるリパーゼの、砂糖はすい臓で分泌されるインスリンの、それぞれ正常な働きに障害を与える。脊髄の一部である胸椎の7番はすい臓に直結していることから、食事が要因で体調不良が起こっていることは明白。改善に必要なのは“最適な食事のシステム”という結論にたどり着いた」と、オーガニックを意識したきっかけを語る。次に行動に移し、“最適な食事のシステム”を具現化できるレシピやメニュー、レストランを探したが皆無で、料理学校も見当たらなかった。そこで「身体にいいものを扱う店を自分で作ろう」と思い立つ。しかし、開業までに8年の期間を要した。「メニューやターゲットを決め、リサーチを行い、プライス設定に細心の注意を払い、それでも簡単に店は開けなかった」と振り返る。
開業した1995年当時はまだ「オーガニック」という言葉は一般化していなかった。「キヨズ・キッチン」では「オーガニック」を全面に掲げたわけではないが、南さんが普段使っていた「オーガニック」という言葉は確実に周囲に波及していった。「オーガニックという言葉を使ったのは、食に対してのみでなく、ライフスタイル全般の問題として用いた。オーガニックという思想や発想のこと」と説明する。開業当初の顧客の反応が興味深い。「珍しい、普段見慣れたメニュー名がない、理解できないといった面持ちの人が多かった。だから普通に店に飛び込んでくる人を見て、ああ、勇気のある人だな、好奇心がある方だなと思った」と南さんは苦笑する。やがて口コミで店の情報は伝わり、“元代々木町にキヨズ・キッチンあり”と言われるほど認知が広がる。現在は東急東横店のデパ地下「東急フードショー」にも店を構え、人気ショップとなっている。
オーガニック・スタイルを提言するショップがなかなか登場し得なかった背景と、オーガニックの商品が手軽に消費者の手元に届けられなかった要因を南さんは次のよう分析する。「工業化は人間の生活を便利にしてきたが、すべてのものを工業化してしまった。本来、工業化してはいけない分野があったはず。それが農業。食の工業化が食に関する様々な問題、さらには精神的な分野にまで悪影響を及ぼした」。飲食業はサービス業の側面を持っているが、健全な第1次産業の側面も併せ持っている。ファーストフードやFC化されたレストランが“工業化”の産物だと定義するなら、第1次産業、つまり農業の延長線上にある飲食店の経営は高いポテンシャルを持ったオーナーが陣頭指揮をとる小規模店舗でしか成立し得なかったとも言えそうだ。
キヨズ・キッチン

1997年、南青山に有機野菜・天然魚介類、ワインもオーガニックワインを提供するレストラン「分土火」がオープンした。同店は1974年に開業した「ビストロダルブル青山」を母体とする「ドカドカグループ」の1店舗。「分土火」料理長の宗像(むなかた)さんは「本当においしいものを求めた結果、自然の食材にたどり着いた」と話す。オーガニックに取り組むきっかけは、宗像さんが1990年から1995年まで経験したフランス・リヨンでの修業にある。「野菜にしろ、ワインにしろ、当時、修業した店のシェフは自然の食材を当たり前に使っていた。その町には誰が採ってもよい栗の木がぽつんとあるなど、すべて自然のままにそこにあった。誰も育ててないのに山に行けばサクランボがあるなど、文字通り無農薬の農作物にあふれていた。目くじら立ててオーガニックを追求したのでなく、それがごく普通の環境だった。農薬を投下しなくてもおいしい農作物が採れたということは、その町の環境に適していたのだろう」と、宗像さんはリオン時代を振り返り、今日への影響の大きさを再確認する。
日本に戻ってきた宗像さんは雑誌の記事で、日本にもオーガニックの野菜を熱心に生産している農家があることを知り、その後、実際に農家を訪ねて回った。「例えば鳥に荒らされる畑がある。それはその土地から生まれる農産物がおいしいからだ・・・などと説明を農家の方から受けるなど学ぶことが多く、しかもそこで食した農作物は実際においしかった。おいしいと感じたものがたまたま有機野菜であったわけだが、それらの土地にも農作物には力があった」。宗像さんは訪ねた有機農法の農家の方々が「土地をつくるということは、自然のものを自然に還すこと」という説明に感銘を受け、こうした農家から「分土火」で扱う食材を直接仕入れ、自身が調理を施した。店はまたたくまに人気店となる。
そして今秋9月には、店頭で有機野菜の販売をスタートした。購入しやすいように小さなパックに詰めて一部の商品を除いて100円均一にするなど、南青山の界隈ではすでに話題を集めている。野菜は朝9時半に全国各地の農家から荷が届き、11時には店頭に並ぶ。店に届いた農産物しか販売できないことや、依頼しても農家が納得しない農作物は届けられないこと、反対に自信作が多く届けられることなど予想しないことが多く、「楽しいやら、大変やら」と宗像さんは苦笑する。「イチジクがおいしかったので再度注文すると、イチジクの木が2本しかないのでもう採れないとか、しし唐がたくさん採れたのでドカンと届けられるなど、農家の人は作意がなく、心からおいしいものを届けたいと願っていることがわかる」と、語る宗像さんは店で始めたばかりの有機野菜の販売に十分な手応えを感じている。
ドカドカ



1998年12月にオープンした代官山の「ECRU(エクリュ)」(渋谷区鉢山町)は、料理とナチュラル・スウィーツで知られるオーガニック・カフェ。ECRU とは「生成」の意味。1990年代末から起こったカフェ・ブーム以降、“オーガニック・カフェ”と銘打ったカフェが数多く登場したが、同店はその先駆者である。野菜、玄米とも農家より直接仕入れを行い、旬の野菜を無農薬農家から直送。ドリンク類もすべてオーガニック。玄米コーヒー、穀物コーヒーなどヘルシーなドリンク類は特に女性に好評。代表の野田さんは20年間、ファッションデザイナーとして活動。20ヶ国近い海外での体験で環境や貧困の問題に目覚め、様々なボランティア活動を始める。さらに心と身体のつながりにも意識が広がり、ヨガ、アロマテラピー、マクロビオティックなど学んでいく。「オーガニックの提案は、フードだけでなく、ライフスタイル全般に及ぶ。オーガニックというライフスタイルを自然に感じ取ってもらうために、以前から何かアクションを起こしたいという思いがあった。そこで情報を発信でき、オープンなスペースで一般の方が情報を得ることのできる場所、フェアトレードなどが践できる場所としてオーガニック・カフェの開業を思い立った」と、開業持のコンセプトを説明する。「ライフスタイルの中でも、特に食べ物が原点」と、開業前に野田さんは店で使う食材を求めて一軒一軒の農家を訪ねてまわったという。千葉の熱田農園や熱海ファームなど、オーガニック農法を実践する農家と出会い、考え方に共感を覚えた野田さんは、オーガニック・カフェのコンセプトを実現化する。「消費者は豊かになっていく過程で、きれいな野菜を求め、虫がついているものを敬遠するようになったが、虫がつくということはおいしい野菜である証拠。流通の問題があり、店ではあまり遠隔地の野菜を扱うことができないが、日本には立派な農家が多く、それに気づいた消費者やマスコミによってオーガニック・スタイルが広まり、現在、確実に浸透しつつある」と、野田さんは展望を語る。
同店ではカフェのほかに、旬の野菜をテーマ「オーガニック・クッキング教室」を開いている。「ヘルシーデザート教室」(1回3,000円)、天然酵母パン教室(1回3,000円)、旬の野菜料理教室(1回 4,000円)。野田さんは「旬の野菜をテーマに据えた料理教室で、野菜のおいしさを発見する機会になっている。玄米にしてもおいしいことをもっと多くの人に知ってもらいたい」と語る。教室には主婦OLはもとより、栄養士や男性も参加している。
ECRU
■裾野が広がるオーガニック・スタイル
今年2月、神宮前にオープンしたオーガニックベーカリー&デリ「アコルト」は、日本初のオーガニック・ベーカリーショップ。代表の松尾さんがベーカリーを担当、パートナーの西野さんがサンドイッチとデリを担当している。同店の特徴は、水に至るまですべての原材料をオーガニックに限定している点。松尾さんは昨今のオーガニック志向の萌芽を「現実問題として実感できていない」と語る。「理由は原材料の確保が大変で、品数が極端に少なく、かつ高価であるから。これは日本の流通の問題がある」と提言する。欧米では流通の10%近くがオーガニックであるのに対し、日本では0.1%に満たないのが現状。値段も非オーガニックと比べると、欧米では約1.3倍なのに対して、日本では2~3倍にも及ぶという。「だからオーガニックでは経営が成り立たないのが実状。オーガニックに対して意識の高い人はもちろん常連客には多いが、5人に1人は値段だけ見て帰ってしまう。意識の高い人とそうでない人の格差が激しく、まだ認識されているとは言えない」と、松尾さんは苦笑する。
「アコルト」開業のきっかけは、現夫人で同店のパートナーである西野さんとの出会い。西野さんと出会い、砂糖と肉、魚、卵、乳製品など動物性の食べ物を口にしない「マクロビオティック」を知り、自身も実践することで食べ物の大切さを実感する。松尾さんは心身ともに充実した生活を送ることが可能になり、以前より興味を持っていたパンの世界に足を踏み入れることになる。「パン作りに妥協はしたくない。例えばパンの素材自体がオーガニックでも、水道水を使っていたのでは純粋なオーガニックとは言えない。パンの1/3は水で出来ている。天然水でなければ本当に安全でおいしいパンはできない」と、松尾さんはすべてにこだわり、また自身にも厳しい。特に原材料の確保について現在、20軒ほどの無農薬有機栽培の農家と直接契約をしているが、それでも足りないという。「無農薬が手に入らなかったら低農薬で代用という考え方は自分にはない。精一杯探してそれでも手に入らなければ欠品にする。実際、デリでは欲しい材料の半分も手に入っていないのが現状」と松尾さん。それでも、オープン以来、着々と常連客が増えている。青山界隈は外国人が多いこともあって「おいしいパンを求めている外国人の方がまとめて購入してくれることがある」という。同店では試食をしてもらい、納得した上で購入してもらうスタイルで商品を販売する。「消費者は味に敏感。いくら安全でもおいしくなければ買ってもらえない」。人気商品はドイツ語で“田舎パン”の意味を持つ「ラントブロート」。全粒粉とライ麦を10%ずつ配合した飽きのこない食事パン。「先日、日本にはおいしいパンがないと諦めかけていた外国人の方に、おいしいと言われて、とても嬉しかった」と松尾さんは素直に喜びを語る。
アコルト2001年7月、日本1号店としてオープンした愛犬家のためのショップ「スリードッグベーカリー代官山店」(猿楽町)は、愛犬用のクッキー、ケーキを販売する専門店。クッキーやケーキは天然素材だけで作られていて、安心して愛犬にプレゼントすることができるとあって全国からファンが訪れる。同店ディレクターの横山さんは「アメリカの本店はもともと愛犬のために何がいいのかを研究した結果、生まれたフードばかり。ビジネスはその次というスタンス。オーガニックの素材ばかりを扱っているわけではないが、自然に近い食材を使い、栄養のバランスに細心の注意を払っているので犬にも最適」と語る。横山さんは天然素材100%のドッグフードを食べた犬の便を見ると、犬の体調がわかるという。「犬にもストレスがあるので、すぐに身体に現れる。『スリードッグベーカリー』のフードを食べるワンちゃんの体調はとても良く、これは人間にも同じことが当てはまる」と話す。
スリードッグベーカリーズ


■「ユニクロ」のアグリ・ベンチャーが渋谷から始動
「ユニクロ」で名高いファーストリテイリングが今秋9月2日、渋谷に農産物や畜産物の販売を新たな会社を設立し、10月3日、事業のブランド名が公表された。新会社の名は「エフアール・フーズ」(道玄坂)、ブランド名を「SKIP」と名づけ、事業を開始したばかり。ファーストリテイリング社長の柳井氏が2000年の記者会見で公言した「新規事業として食品などがおもしろい」という言葉が実際に事業化されたのである。同社広報担当の河野さんは「もともと衣食住を意識し、消費者に近いところでビジネスを展開するのがファーストリテイリングの考え方。その発想は他のビジネスモデルでも使えるのではないかと考えたわけです。高品質で低価格であること、そして生産者と消費者を直接結びつけることが『ユニクロ』との共通点」と説明する。同社の代表を務める柚木氏はファーストリテイリング社のダイレクト事業部で活躍していたが、柳井氏の発言を受け、自身がその業務を担当したいと名乗りを上げた社内起業家。柳井氏に自身が考える食品事業の提案をし、“永田農法”で著名な永田さんの協力を得るなど事業化に邁進してきた。
ブランド名の「SKIP」を命名したのはコピーライターの糸井重里氏。糸井氏はネーミングだけでなく、コミュニケーション全般を担当している。「SKIPとネーミングされたのは、食べることは本来スキップしたくなるくらい楽しいことで、そういう原点に立ち戻ろうという意味と、生産者と消費者を結びつけているものの間をスキップするという意味、さらにスローフードほどゆっくりはできないが、スキップくらいのスピードで生きていこうといったメッセージが込められている」(河野さん)。「SKIP事業」の基本となっているのは(1)通販 (2)移動販売である。通販にはインターネット販売と15,000人限定の会員組織「SKIPクラブ」があり、移動販売には「テントストア」と「トラックストア」がある。テントストアとは首都圏中心に「ユニクロ」店舗の駐車場や駅前などにテントを張って野菜を販売する形態のショップ、トラックストアとはトラックに積んで各地に販売に出向く形態のショップのこと。「いずれリアル店舗を出店したいと考えている。現在はいろんなところで消費者と対面し、実際の声を聞くことのできる販売を心がけ、その声を事業にフィードバックするよう考えている」(河野さん)と、消費者に近い場所に出向き、直に耳を傾けている最中である。「スーパーと同じくらいの価格のものから少し高いものもあるが、多くの人に安心でおいしいものを食べてもらいたいと願っている。SKIPはいわば消費者と生産者の橋渡し役。農家の栽培履歴をネットに掲載するなど安全検査情報を公開しているのも新たな試み。安全のために、すべての農業家の、すべての品目、季節ごとに栽培履歴を記録、公開し、SKIPの検査基準をクリアできなかった作物は販売しないという姿勢で臨んでいる。ゆくゆくはSKIPがつきあっている農家だから信頼できる、と言われるようなブランドになりたい」と河野さんは抱負を語る。
SKIPオーガニック野菜はもともと可処分所得の高い消費者が購入する、ある種特別な食材であった。オーガニックは品数が少なく、流通も整備されていないことから末端価格は高価となり、一般消費者が手にしにくい環境にあった。それが近年、食品の偽装表示事件が多発し、消費者の目は信頼のおける生産者の手によって生まれた有機農産物へと向かった。流通インフラの整備や、有機栽培農家を訪ね、本当に安全でおいしい食べ物を提供すべく、努力を惜しまなかった飲食店オーナーなどの存在により、じわじわと日常の食生活に「オーガニック・スタイル」が浸透してきた。
青山・代官山・広尾を含む広域渋谷圏には、もともと食を含めたライフスタイルにこだわりを持つ消費者が多く、彼らが安心でおいしい食べ物を求めるのは自然の流れでもあった。今、まさに「オーガニック・スタイル」がファッションになりつつある。感度の高い情報として「オーガニック・スタイル」が全国へ波及することで流通整備が加速すれば、価格の低廉化にもつながる。当然ながら、大手企業も「オーガニック・スタイル」に目を向けている。しかしながら、オーガニック・マーケットを工業製品的なメーカー的な発想で捉えるのは難しい。ごく自然に安全と健康を願う消費者の視点が今後の鍵を握る。