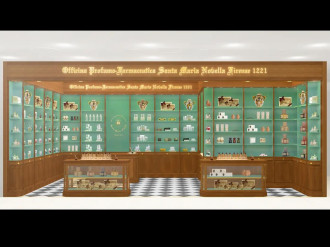千駄ヶ谷のラーメン店「ホープ軒」が50周年 屋台から「一日も休まず」

ラーメン屋台で始まり、長年親しまれてきた千駄ヶ谷のラーメン店「ホープ軒」(渋谷区千駄ヶ谷2、TEL 03-3405-4249)が1月21日で50周年を迎えた。
国立競技場の真向かいに立つ黄色いビル。今年2月で86歳になる店主の牛久保英昭さんは今も毎日、厨房(ちゅうぼう)に立つ。「赤羽で屋台を始めてから丸15年と1日、休むことなく屋台を引き続けて、1975(昭和50)年1月21日に今の場所に店を出した」と振り返る。
1939(昭和14)年2月18日、浅草・千束生まれ。大戦中には大空襲に遭い他県に逃れるなどする中、卒業後は渋谷・宮益坂のパン店や錦糸町の駄菓子店などで生計を立て、20歳の時にラーメン屋台を引き始めた。そこから1カ月ほどで現「ホープ軒本舗」の貼り紙と出合う。「当時東京で20~30軒ほど屋台があったんじゃないかな。こっちの方が面白そうだなと思った」と、ホープ軒の屋台に乗り換えた。
牛久保さんが作り上げたのは、しょうゆ豚骨スープに背脂をのせた「背脂(チャッチャ)系」と呼ばれるラーメン。同じホープ軒の屋台でも「麺は一緒だったが、みんなスープは違った。屋台の小さな設備の中で作るから、そこに水を足したり追いだしをしたり…いろいろな工夫をして朝まで持たせる。個人個人みんな味が違った」と言う。そうした中、牛久保さんは中華そばに代表される当時主流だった透明なスープに対し、豚骨を白濁するまで煮出して作るスープを考案。銀座や赤坂などを経て、旧NHK社屋や新聞社などが集まる内幸町で屋台を続けた。
屋台を「卒業」し、店を構えることになった際、千駄ヶ谷を選んだ理由について、「すぐ近くのマンションに住んでいた。タクシーの運転手が車でも寄りやすい所がいいと思い、不動産屋に聞いたらここを紹介してくれた。競技場はあったが、車通りも人通りも多くなかったのが良かった」と話す。最初に借りたのは、3階建てのビルの1階部分。運転手や記者など「忙しい人たち」が主な客層だったこともあり、現在も残る立ち食いスタイルを選んだ。
「大抵の店が終わる時間帯になると、タクシーがいっぱい集まってきて、店の前が一つのターミナルのようになる。『あそこのラーメン屋の所に行けば運転手がいっぱいいる』となって、そこから乗って帰ろうとするお客さんもいたし、タクシーの運転手からしても、『ラーメンを食べられるならお客さんもまだ元気で居眠りもしない』とここに来る。そんな感じだった」
その後、1989(平成元)年に同ビルを購入し、隣の空き地に仮店舗を作り営業を続けながら、ビルを建て替えたという。現在のビルは4階建てで、2階・3階には着席スタイルのカウンターやテーブル、4階には製麺室を設ける。「2階に客席を作っても、(忙しい来店客が)上がってきてくれるかなと思って本当に心配だった。最初は町内会から仮のテーブルを借りてきて並べて様子を見ていたら、2階にもお客さまが入った。そうすると、やはり客層が変わってきた」と変化も訪れ、口コミなどもあり、徐々に客層が広がっていったと言う。
漫画家の故・横山泰三さんも常連客の一人で、漫画家の仲間らと共に、よく店を訪れていたと言う。ビルの看板やスタッフTシャツに描かれている「ホープ軒」の書体と豚の絵も、横山さんが手がけたもの。「屋台を始めた頃からの常連で、いろいろと面倒を見てくれた」と懐かしむ。
屋台時代も一日も休まなかった牛久保さん。千駄ヶ谷に店を構えてからも「50年間、一日も店を休んでいない」と言い、「コロナ禍の時もうちはやっていたから、かえって忙しかったかもしれない。『ホープ軒は365日やっている』という信頼は絶対にある。あそこは何があっても、嵐でも、いつ行っても、必ずやっているんだから、という信頼がある」とも。
時代の移り変わりに合わせて、値上げにも柔軟に対応してきた。「タクシーと首都高の初乗り料金に合わせて変えてきたが、今はもう別。人件費が特にかかる」と、現在ラーメンは1,000円で提供している(チャーシュー麺・ワンタン麺=1,300円ほか)。機械を導入し作業の効率化なども考える一方で、「やっぱりそこに人の情熱みたいなものがないと」と、人情も大切にしたいという思いは変わらない。
「そろそろ休んでどこかに伸び伸びと旅行に行きたい」と笑顔を見せるが、「でも今は毎日働いていないと、きっと衰えていってしまう。長い時間じゃなくても、忙しい時間だけ手伝って『ここに使ってもらっているんだ』という気持ちでやっている」と昼夜厨房に立つ。牛久保さんを見つけると喜ぶ来店客も多く、「何か不測の事態が起きても、私がいることで、お客さまに安心してもらえたらうれしい」と話す。
24時間営業。